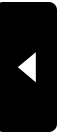2008年11月26日
放流?②
本州でのブラックバスの問題、北海道でのブラウンの問題というのは、結局のところ水産業界と釣り業界の、漁師と釣り人の対立だよね。表面的には、環境問題などが取り沙汰されるけど、根っこにあるのは業界同士のぶつかり合いだよね。ブラックバスをめぐっての騒動や、某雑誌の記事に見られるブラウンに関する協議会の内容は、詰まるところは漁師と釣り人が、それぞれの対象魚に対する影響を巡って対立していると言えるのでは?
少なくとも、某雑誌がブラウンのことを記事にするとき、いつも不可解に感じるのが、すでに生息環境の回復をあきらめているかのようなことを書いていること。
「ブラウンを駆除してしまったらそこに魚は残らない」
実にあっさりとそんな科白が記事に載せられているよなぁと思ってしまう。
じゃぁ、その一方でダムの反対運動に加担するかのような記事を書き、個別の記事でも河川環境の大切さを訴えるのはなぜ?
屈斜路湖ではアメマスの放流歴がないにもかかわらず、アメマスが戻ってきた、ということを記事にしていたのでは?
長く釣りをやっているのであれば、以前よりも魚が釣れるようになったと実感できる川は少なからずあるんじゃないだろうか?それは、多少なりとも、地元や保護団体などの活動の成果ではないのか?
魚道の荒廃を憂いている記事を散々書いていながら、ブラウンの記事ではなぜあきらめきっているような書き方をするのだろう?
不思議だね。河川環境を取り戻そうとは思わないのか?
穿った見かたになるかもしれないけど、『ゾーニング』という、まことしやかな単語を使ってはいるものの、河川環境を取り戻すことよりもブラウンを駆除させないことを優先しているように感じてしまう。
『ゾーニング』の前提として水系の分断があるように見える。戸切地川で言えば、上磯ダムを境にして魚の往来を阻止しないと、ゾーニングは不可能に思える。
読むたび、そこに大きな矛盾を感じてしまうのは俺だけかな?
少なくとも、某雑誌がブラウンのことを記事にするとき、いつも不可解に感じるのが、すでに生息環境の回復をあきらめているかのようなことを書いていること。
「ブラウンを駆除してしまったらそこに魚は残らない」
実にあっさりとそんな科白が記事に載せられているよなぁと思ってしまう。
じゃぁ、その一方でダムの反対運動に加担するかのような記事を書き、個別の記事でも河川環境の大切さを訴えるのはなぜ?
屈斜路湖ではアメマスの放流歴がないにもかかわらず、アメマスが戻ってきた、ということを記事にしていたのでは?
長く釣りをやっているのであれば、以前よりも魚が釣れるようになったと実感できる川は少なからずあるんじゃないだろうか?それは、多少なりとも、地元や保護団体などの活動の成果ではないのか?
魚道の荒廃を憂いている記事を散々書いていながら、ブラウンの記事ではなぜあきらめきっているような書き方をするのだろう?
不思議だね。河川環境を取り戻そうとは思わないのか?
穿った見かたになるかもしれないけど、『ゾーニング』という、まことしやかな単語を使ってはいるものの、河川環境を取り戻すことよりもブラウンを駆除させないことを優先しているように感じてしまう。
『ゾーニング』の前提として水系の分断があるように見える。戸切地川で言えば、上磯ダムを境にして魚の往来を阻止しないと、ゾーニングは不可能に思える。
読むたび、そこに大きな矛盾を感じてしまうのは俺だけかな?
Posted by あに at 11:54│Comments(4)
│おしゃべり
この記事へのコメント
こんばんは、2回目のコメントです。
某誌のダム、魚道などに関する記事、問題提議について、私は評価していますし、共感できる面も多いと思っています。問題視されているブラウンに関する記事ですが、私も読んでいてちょっと違和感を感じていました。まったく的外れなことかもしれませんが、このブラウンの記事を目にした時にふと思ったのが「マッチ・ポンプ」という言葉です。某誌の編集者は「勝手に放流しておいて、今度は駆除かよ、それってどうよぉ?」ってことを駆除を率先してやってる団体に言いたかったのかな、と思った記憶があります。その号が手元になく、読み返していないので、アホなコメントになっていたらすいません。いつになくあに
さんが熱く語っておられたので…。
某誌のダム、魚道などに関する記事、問題提議について、私は評価していますし、共感できる面も多いと思っています。問題視されているブラウンに関する記事ですが、私も読んでいてちょっと違和感を感じていました。まったく的外れなことかもしれませんが、このブラウンの記事を目にした時にふと思ったのが「マッチ・ポンプ」という言葉です。某誌の編集者は「勝手に放流しておいて、今度は駆除かよ、それってどうよぉ?」ってことを駆除を率先してやってる団体に言いたかったのかな、と思った記憶があります。その号が手元になく、読み返していないので、アホなコメントになっていたらすいません。いつになくあに
さんが熱く語っておられたので…。
Posted by lureman140 at 2008年11月26日 20:03
lureman140 さんごぶさたです
もちろん河川環境改善に対する取り組みは評価できますが、その取り組みが記事によっては無視、あるいは「できないよ」と言わんばかりでは、雑誌として、社としてのイズムに書けると感じてます。
いや、それ以上に護りたいのは釣れる魚、なのでしょうが、この記事を書いている本人が、ブラウンを放流して回っているという噂もあるだけに、書いてある事だけを信じるつもりにはなれません。というか、全く同意できない。
もちろん河川環境改善に対する取り組みは評価できますが、その取り組みが記事によっては無視、あるいは「できないよ」と言わんばかりでは、雑誌として、社としてのイズムに書けると感じてます。
いや、それ以上に護りたいのは釣れる魚、なのでしょうが、この記事を書いている本人が、ブラウンを放流して回っているという噂もあるだけに、書いてある事だけを信じるつもりにはなれません。というか、全く同意できない。
Posted by あに at 2008年11月30日 08:00
at 2008年11月30日 08:00
 at 2008年11月30日 08:00
at 2008年11月30日 08:00「本人がブラウンを放流して回っている」。
何を根拠にそんな噂を書き込んでいるのでしょうか?僕としては某雑誌の記事は共感できますし、逆に自称、「俺」の記事はまったく共感できませんね。この様に人それぞれ考え方はあるわけですから、ブラウンを叩きたい
のか、一個人を叩きたいのかよくわからない記事ですね。
同じトラウトでありながらブラウンのみが駆除の対象。ただ単純に、人として心が痛みます。
何を根拠にそんな噂を書き込んでいるのでしょうか?僕としては某雑誌の記事は共感できますし、逆に自称、「俺」の記事はまったく共感できませんね。この様に人それぞれ考え方はあるわけですから、ブラウンを叩きたい
のか、一個人を叩きたいのかよくわからない記事ですね。
同じトラウトでありながらブラウンのみが駆除の対象。ただ単純に、人として心が痛みます。
Posted by つり太郎 at 2008年11月30日 17:41
コメントありがとうございます。
つり太郎さんご自身がお書きのように、それぞれに共感できる考え、共感できない意見というのはおありでしょう。それはおっしゃる通り。
じゃぁ、接点を持たなければ良いじゃないか?なんてことも言えそうですが、それでは、自分がブログを書いている意味も、つり太郎さんがわざわざコメント書いていただいた意味もありませんしね。
なので、頑張ってお答えいたします。
まず、本人が放流しているという噂ですが、いくつかのサイトを検索していれば引っかかってきます。「根拠は?」と申されますが、あらかじめお断りしているように、それは「噂」です。
私のブログは論文でもプロパガンダ目的でもなく、自身の釣りに関する、究めて個人的な内容のブログです。この記事についてもあくまでも私見をつらつらと書き連ねているに過ぎないのですから、ソースの提示までに責務を負うとは思いませんし、その必要性もないでしょう。その程度のレベルのブログですから。
私がここで書いているのは、あくまでも「ブラウンに関する某雑誌の記事」について、私自身の感じている違和感なのです。その違和感について、前述の「噂」を絡めて見ると、「ああ、だからこういうことを書くのか」と、なんとなく感じることができるように思えてはいます。故にこのような形で記事にし、コメントに掲載しています。
逆に、その「噂」を否定できるだけの材料を私は持ち合わせているわけではありませんし、また記事を書いたご本人が放流していないとしても、明らかに規制のかかった後での、規制に触れる放流行為によって生息域が増えているという事象に対しては、少なくとも否定的な立場にはいないようです。まぁそこにも違和感を持ってはいます。
そして、残念ながら読み落とされていると私は感じていますが、あくまでも記事を書くきっかけになっているのは「ブラウンの記事」ですが、私自身は、ブラウン以外の魚種の放流、それは外来種だけではなく、在来種であっても問題を含むものはあると感じています。念のため。
それから、「駆除されるブラウンに罪はない」。それはその通りだと思いますよ。ですが、そのことと「ブラウンを勝手に放流している」という行為は別の次元の問題だと思います。それぞれは「生命の尊重」と「ルール違反」です。
ブラウンそのものに対して、私は悪意や否定的な考えを持っているわけではありません。違和感を感じているのは、ほとんどがルール違反の放流であろう行為によって生息域を拡大しているという既成事実に乗っかって、つり太郎さんのおっしゃるような「生命の尊重」を盾に、既成事実化しようとしているように感じられることに対してです。
つり太郎さんご自身がお書きのように、それぞれに共感できる考え、共感できない意見というのはおありでしょう。それはおっしゃる通り。
じゃぁ、接点を持たなければ良いじゃないか?なんてことも言えそうですが、それでは、自分がブログを書いている意味も、つり太郎さんがわざわざコメント書いていただいた意味もありませんしね。
なので、頑張ってお答えいたします。
まず、本人が放流しているという噂ですが、いくつかのサイトを検索していれば引っかかってきます。「根拠は?」と申されますが、あらかじめお断りしているように、それは「噂」です。
私のブログは論文でもプロパガンダ目的でもなく、自身の釣りに関する、究めて個人的な内容のブログです。この記事についてもあくまでも私見をつらつらと書き連ねているに過ぎないのですから、ソースの提示までに責務を負うとは思いませんし、その必要性もないでしょう。その程度のレベルのブログですから。
私がここで書いているのは、あくまでも「ブラウンに関する某雑誌の記事」について、私自身の感じている違和感なのです。その違和感について、前述の「噂」を絡めて見ると、「ああ、だからこういうことを書くのか」と、なんとなく感じることができるように思えてはいます。故にこのような形で記事にし、コメントに掲載しています。
逆に、その「噂」を否定できるだけの材料を私は持ち合わせているわけではありませんし、また記事を書いたご本人が放流していないとしても、明らかに規制のかかった後での、規制に触れる放流行為によって生息域が増えているという事象に対しては、少なくとも否定的な立場にはいないようです。まぁそこにも違和感を持ってはいます。
そして、残念ながら読み落とされていると私は感じていますが、あくまでも記事を書くきっかけになっているのは「ブラウンの記事」ですが、私自身は、ブラウン以外の魚種の放流、それは外来種だけではなく、在来種であっても問題を含むものはあると感じています。念のため。
それから、「駆除されるブラウンに罪はない」。それはその通りだと思いますよ。ですが、そのことと「ブラウンを勝手に放流している」という行為は別の次元の問題だと思います。それぞれは「生命の尊重」と「ルール違反」です。
ブラウンそのものに対して、私は悪意や否定的な考えを持っているわけではありません。違和感を感じているのは、ほとんどがルール違反の放流であろう行為によって生息域を拡大しているという既成事実に乗っかって、つり太郎さんのおっしゃるような「生命の尊重」を盾に、既成事実化しようとしているように感じられることに対してです。
Posted by あに at 2008年12月02日 01:43
at 2008年12月02日 01:43
 at 2008年12月02日 01:43
at 2008年12月02日 01:43※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。